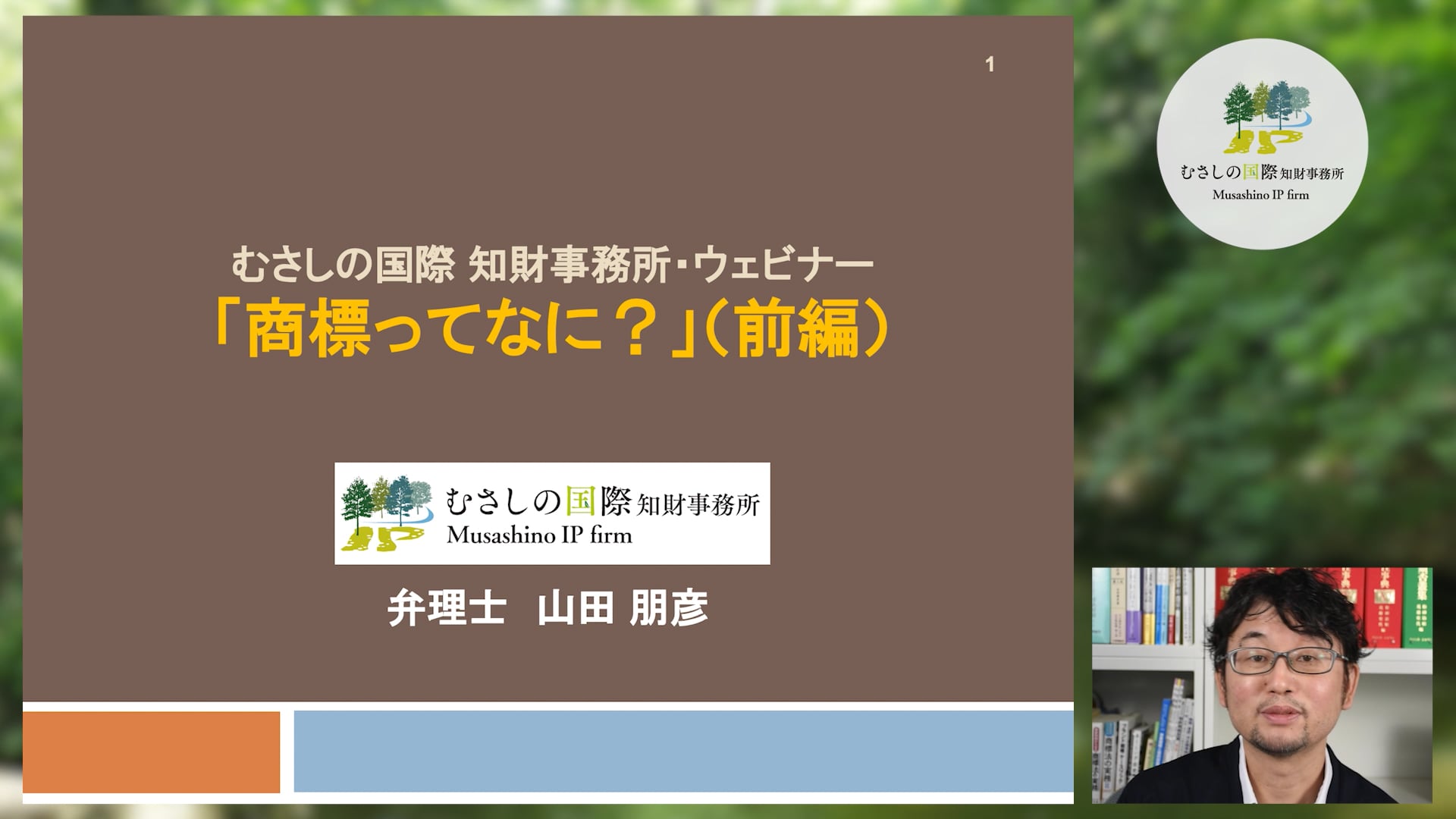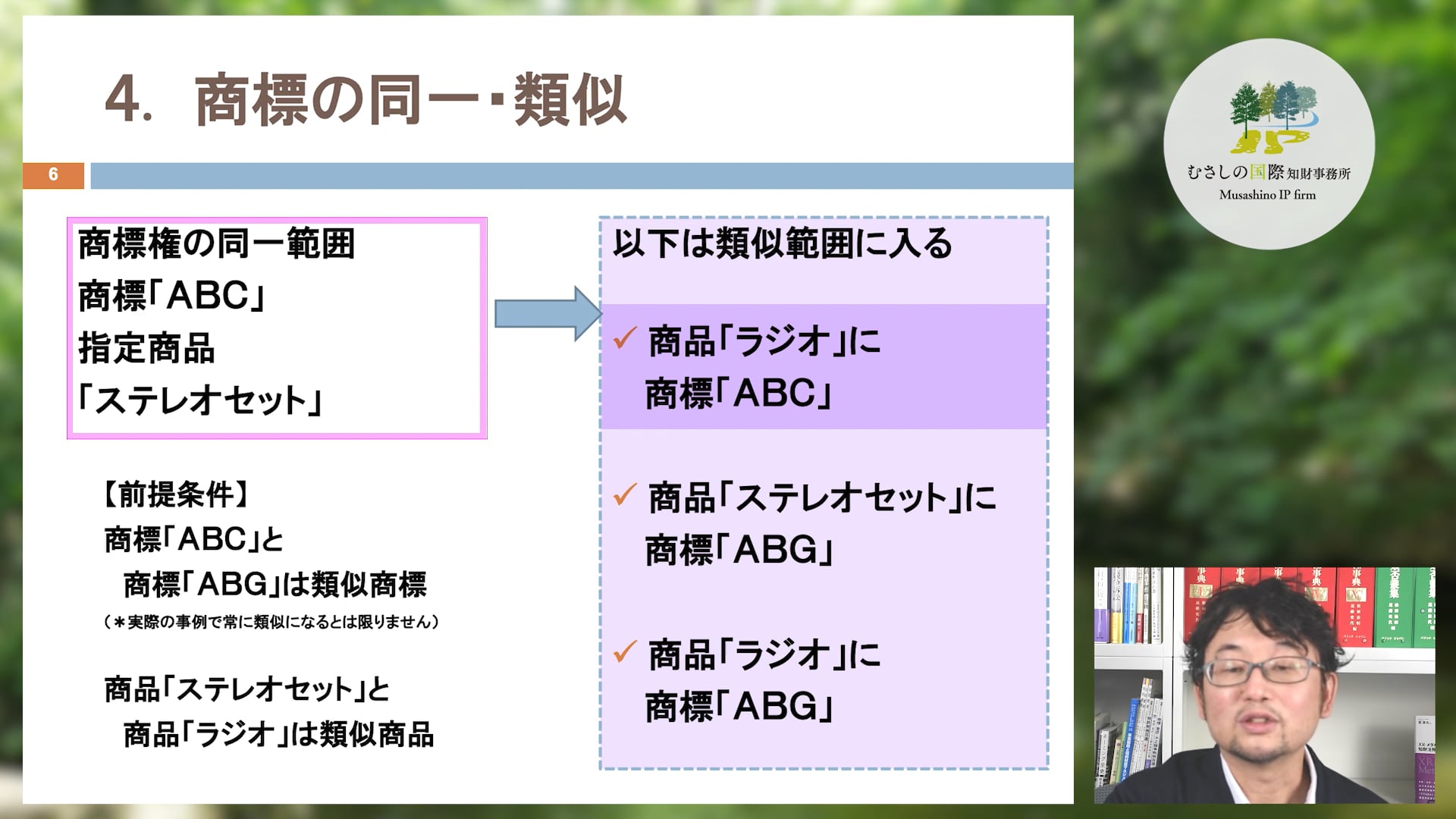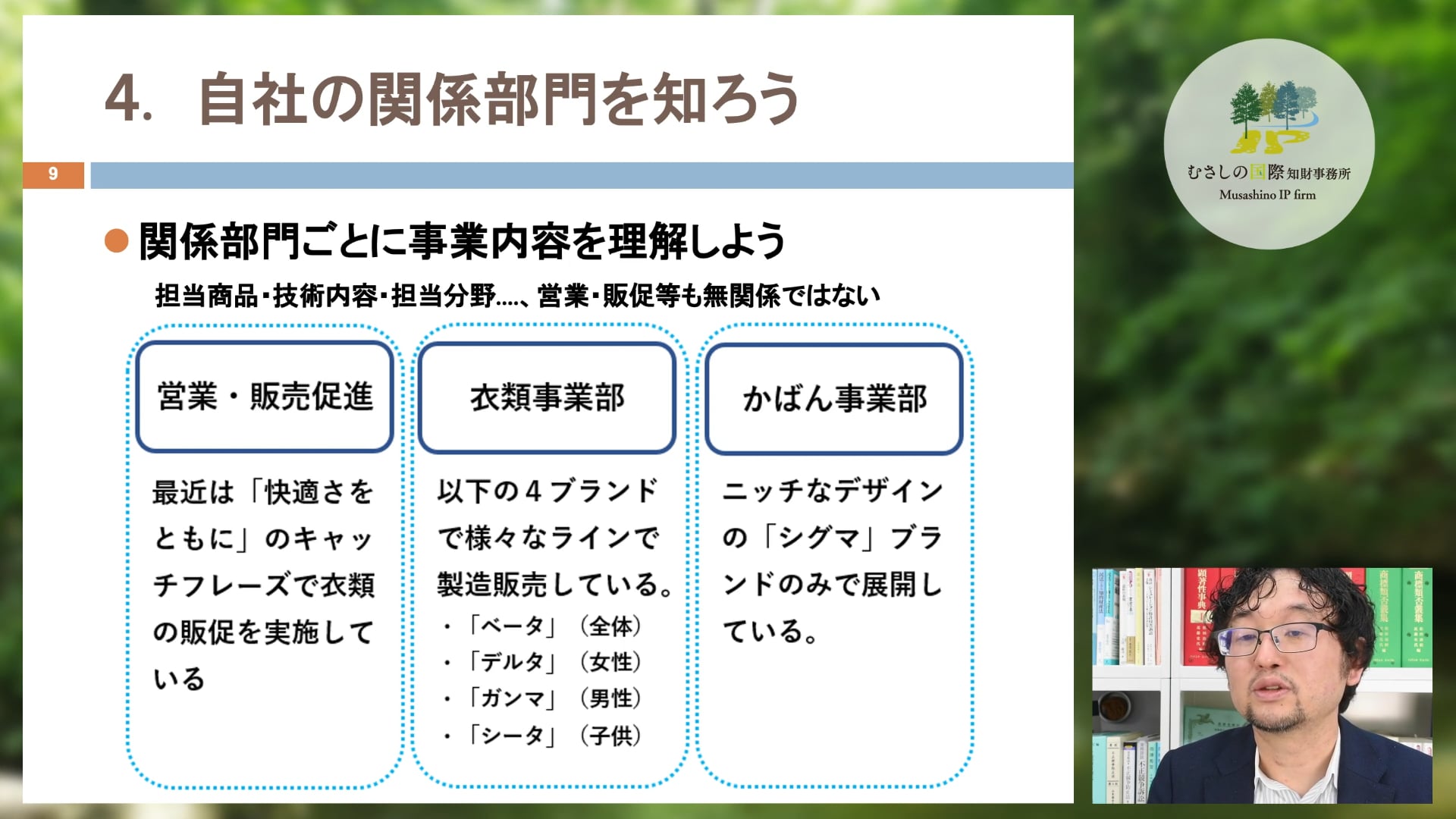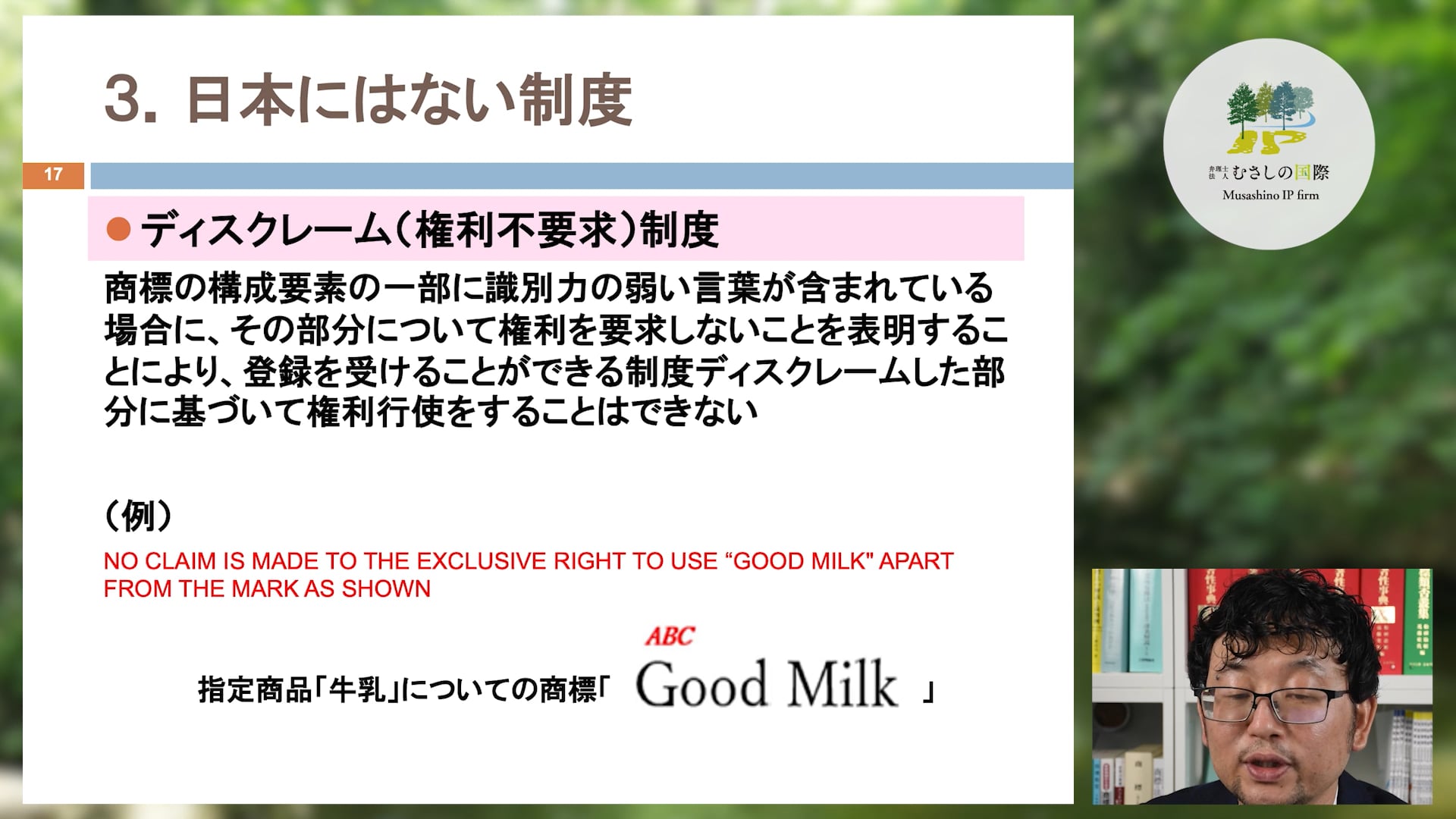代表 山田 朋彦
国内外の商標・意匠関連業務を専門とする。出願・権利化業務だけではなく、当事者系審判、権利侵害対応、ドメイン紛争等の争訟や交渉等に関する業務も多数取り扱う。また、外部活動や講師・講演活動等の豊富な経験を生かして、企業内セミナーや補助金申請の助言等、企業内の知財業務のサポートも行う。(続きは「+」をクリック)
経歴
・1998年:岐阜県立岐阜高等学校卒業
・2002年:東京外国語大学外国語学部ロシア語専攻卒業
・2003年:都内特許事務所にて勤務開始
・2003年:弁理士登録(登録第13050号)
・2005年:東京外国語大学大学院地域文化研究科修了
・2011年:特定侵害訴訟代理業務付記
・2021年:むさしの国際知財事務所開設
・2023年:弁理士法人むさしの国際設立
主な外部活動
・日本弁理士会 商標委員会委員長(2019年度)
・日本弁理士会 商標委員会副委員長(2015~2018年度,2024年度~)
・日本知的財産仲裁センター JPドメイン名紛争処理パネリスト候補者(2025年度~)
・特許庁審判部 審判実務者研究会委員【商標】(2014~2015年度)
・日本貿易振興機構 外国出願支援事業審査委員【商標】(2020~2023年度)
・発明推進協会 中小企業等海外展開支援事業費補助金事業審査委員【商標】(2024年度~)
・商標五庁(TM5)中間会合 User’smeeting派遣(2017年)
主な講師・講演活動
・日本弁理士会 「実務修習(商標分野)」
・日本弁理士会 「商標実務の勘所と最新商標情報」
・国際協力機構 「代理人視点からの日本の商標制度」
・エンターテインメントローヤーズネットワーク「商標とエンターテインメント業界」
・PA会研修 「ニュース・報道で学ぶ商標実務」
主な著作活動
・『最新判例から見る商標法の実務II[2012]』(青林書院・2012・共著)
・「ノベルティに使用する商標について」(知財管理・2017)
・「商標審査基準改訂の解説」(パテント・2018)
・「小売等役務制度に関する事例紹介と今後の課題について」(パテント・2020)
・『重要判例分析×ブランド戦略推進 商標の法律実務』(中央経済社・2023・共著)